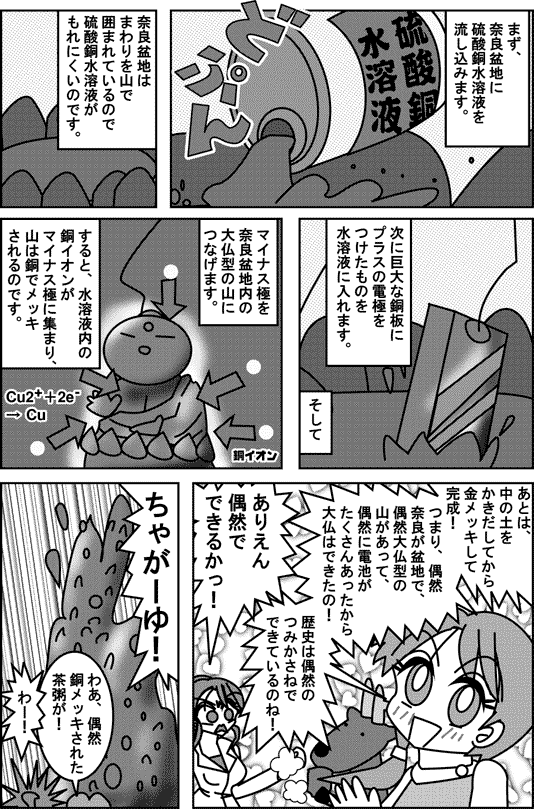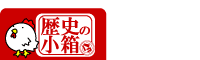|
質問者 ● Shi.Ma.Chuさん
|
奈良近辺に都が乱立した中、平城京時代を奈良時代と
特別に呼ぶ理由はなぜか。 |
確かに2ページ目のように、聖武天皇時代にはあちこちに遷都しました。
恭仁京(京都府)、紫香楽宮(滋賀県)、難波宮(大阪府)、
ほかにも淳仁天皇時代には保良宮(滋賀県)が使用され、
称徳天皇時代には由義宮(大阪府)の建設なども行なわれました。
また、桓武天皇が平安京に遷都する前に長岡京(京都府)に遷都した年代も
奈良時代と呼ばれています。
奈良時代の天皇は元明、元正、聖武、孝謙、淳仁、称徳(孝謙重祚)、光仁、桓武の8代です。
うち後期の4代では奈良以外にも都がおかれているのです。
これを見ると奈良時代を通して奈良に都があったわけではありません。
では、なぜ奈良時代というのでしょうか。
それは、奈良に都を置いていない時期にも、奈良には重要なものがあったのです。
一体奈良にはなにがあったのでしょうか。
それが、おるすばんです。
天皇や貴族達が都から去っても、一人奈良で待つ、おるすばんが存在しました。
学校から帰っても誰もいない都で一人、夕食をレンジでチンして待つ、おるすばん。
なんてかわいそうな。そんな彼に敬意を表してこの時代を奈良時代というのです。 |
|