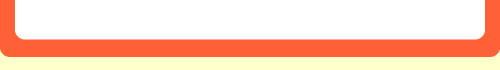2007年9月8日分
このコーナーは皆様から寄せられた科学的な質問に科学的にあくまで真摯に答えるコーナーです。
これまでのまめぎもんスペシャル
2007年6月9日分
2007年7月14日分
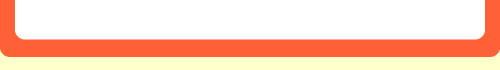
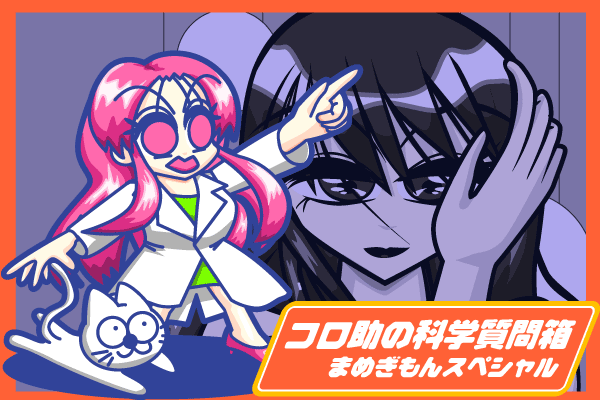

2007年9月8日分
このコーナーは皆様から寄せられた科学的な質問に科学的にあくまで真摯に答えるコーナーです。
これまでのまめぎもんスペシャル
2007年6月9日分
2007年7月14日分
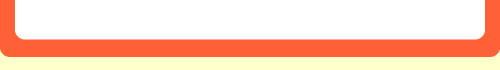
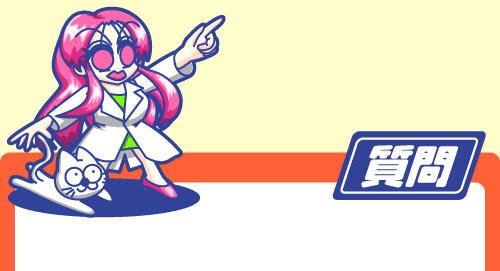
えんぴつは何時出来たのですか?
壁下実乃梨さんのご質問

鉛筆というのは、黒鉛でできた芯を木ではさんだ筆記具です。
なぜ鉛筆は木ではさまれる必要があったのでしょうか。
鉛筆の芯を素手でさわってみるとわかりますが、黒鉛をじかに触ると手が汚れてしまいます。
そこで木で黒鉛をはさんで汚れにくくしたのが鉛筆の始まりなのですが、いったいそれは誰が考えたのでしょうか。
それは、イギリスの海軍卿を務めた貴族、第四代サンドウィッチ伯爵・ジョン・モンタギューです。
サンドウィッチ伯爵はたいへんポーカーと競馬が好きで、ポーカーをやっている最中に軽い食事をとれるように、パンで具をはさんだサンドウィッチを発明し、マークシートに黒鉛で印をつけられるように、木で黒鉛をはさんだ鉛筆を発明したのです。
ですから鉛筆の発明は、サンドウィッチ伯爵の在世中である18世紀中盤から後半であると考えられています。
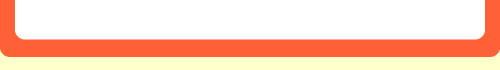
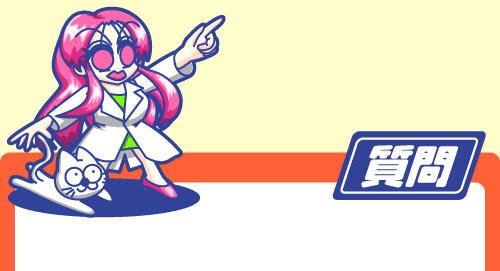
どうして40度のお湯と100度のお湯をたしても
70度にならないんですか?
かりんさんのご質問

これは、お湯の温度というものがどんなものであるかを考えなくてはなりません。
100度のお湯というのはその水全体が100度になるほどの熱量を持ったもので、40度のお湯というのはその水全体が40度になるほどの熱量を持った状態を指します。
1リットルの水を○であらわし、ひとつの水の温度を20度上げる熱量を△であらわしますと、このようになります。
100度のお湯5リットル
○○○○○
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
○は5個、△は25個です
40度のお湯2リットル
○○ △△△△
○は2個、△は4個です。
このふたつの水を足すとこうなります。
○○○○○○○
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
△△△△
○は7個、△は29個です。
△は○ひとつを20度上げる力があるのですから、△を○で割ってみると全体の温度が出るわけです。
29÷7=およそ
4.1、 ○一個に対して△が4.1、△一つは20度なのですから82度となります。
つまり水の温度のほかに水の量も重要となるわけです。
この式でいくと100度の水と40度の水が同じ量であれば70度になるわけです。
しかし、実際にはこの式のほかにも様々な問題があります。
たとえばお湯の温度は何もしなくてもどんどん下がっていきます。これは空気中にお湯の温度が逃げ出すからです。
ここで逃げ出す温度を■とします。これを考えると結果から■分の熱を引かなければなりません。また、ホットメルト団の存在があります。ホットメルト団は地球上のあらゆる水をお湯にしようともくろむ悪の秘密結社です。彼らは手にしたたいまつで水を加熱しようとします。ですから結果にホットメルト団のたいまつにより加えられる熱を足さなければなりません。これを〒とします。
このほかにも※や▽や☆や仝などの存在を考えなければなりません。したがって70度ぴったりになるのはかなり遠い道のりであることはわかっていただけるでしょう。
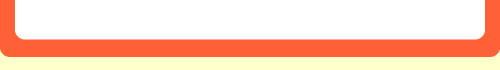
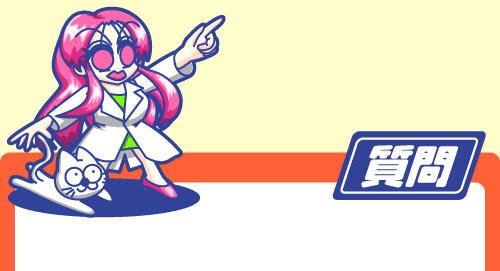
・セロファンを通していろいろな色を見るとちがって見えるのはなぜか?
・ヒトは色をどうやって見分けているんですか?
・動物によって同じ色を見ても見え方がちがうのか?
・音と同じように色にも見えない色はあるのか。
・人間には見えない色を感じる動物はいるのか。
(紫外線や赤外線を見ることのできる動物はいるのか)?
・超音波について,大人に聞こえない音は本当にあるか。
・動物によって聞こえる音がちがうのか。
・インターネットで大人に聞こえない音14000Hz以上(イギリスの記事)というの がはある。と書いてあったが,それは本当か。なぜ,このような現象が起こるのか?
山本則夫さんのご質問

かつて、聖徳太子という人がいました。
彼は10人の人から別々のことをいっぺんに言われてもすべて聞き分ける能力を持っていたと言います。
そこで聖徳太子のひそみにならって、一度に寄せられた質問に一度に答えてみたいと思います。
「それが、人というものだから。」
納得がいかないという方もいらっしゃると思いますが、人という時は人と人が支え合っているのだということをご考慮いただければ幸いです。
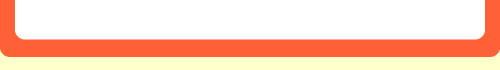
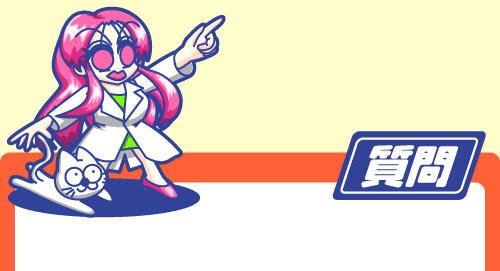
放射能の半減期について質問します。核爆弾の爆発によって
放出される放射能は、半減期が何千年、何万年とかかるもの
がほとんどだと思いますが、広島・長崎に原爆が投下されて
からほんの数十年しか経っていないのに、
何故普通に人が暮らせるのですか?
半減期が何千年もかかるのであれば、現地は有害な放射能で
満たされて人は住めないはずだと思うのですが?
AAAさんのご質問

原子爆弾というのはウランやプルトニウムのような放射性物質が核分裂する際に多大なエネルギーを放出することを利用した爆弾です。
また、放射性物質は放射線を出しながら崩壊して別の物質に変わります。
この際、元の物質が半分の量になる時間を半減期といいます。
兵器として使われるウラン235は半減期7億年、プルトニウム239は2万4000年です。
しかし、広島や長崎にこれらの物質をまんべんなくまいたわけではありません。
広島型の場合はウラン60キログラム、長崎型はプルトニウム8キログラムほどでした。放射線だけで全市を死の街とするほどの量はありません。
また、これらは核分裂の際に別の物質となります。
ウラン235は中性子線を出してクリプトン92とバリウム141になり、さらにそれらは崩壊して別の物質となります。
主に残留放射線被害を出したのはそれらの核分裂の際に生まれた核分裂生成物です。
ウランやプルトニウムから分裂して生まれる核分裂生成物は量も多く、放射線を放つ力を持っていますが、長いものでも半減期は30年、短いものでは数秒ほどでした。
さらに大きな要因としては、砂漠ではない天然の状況では風雨による拡散があります。これで残留放射能はかなり薄まります。
さらにもみじ饅頭があります。もみじの中にあんこが入ったもみじ饅頭は、放射能のことをみじんも感じさせません。そして広島の良さを主張する際に、ただこれらの名前を連呼するだけの人も現れます。これらの屈託のなさが放射線の影響を弱めるものだとも考えられます。長崎についてはカステラに卵黄をつけて糖蜜で揚げたカスドースがあります。それは平戸市名物ではないかという意見もありますがともかく屈託を感じさせないことが重要であるとの指摘があります。
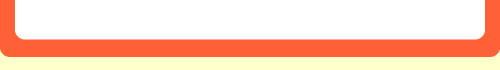
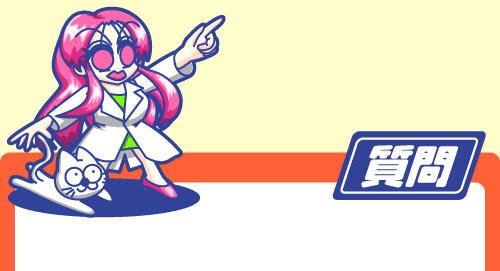
火ってなんですか?
・
どうして光と熱を発するんですか?
・
その光と熱はどこからくるんですか?
・
どうして上向きに火は燃えるのですか?
・
その火に触れると、どうして他のものが燃えてしまうのですか?
ありーるさんのご質問

先ほどのまとめて回答スタイルが一部で大変な不評であるというご指摘をいただきました。
そのようなご指摘をうけたのはたいへん不本意ではありますが、今度からは回答の姿勢をあらためていきたいと思います。
・火はどうして光と熱を発するのか?
火というのはそういうものだからです。光や熱と言った貴重なものを惜しみなく放出するのは人間では考えられません。そうしたものを放出することで何か新たなものを表現しようとしているのだと言われています。その表現にかける情熱だけは確かなものでしょう。
・その光と熱はどこから来るのか?
火がそれを求めたからというより、そうさせたのです。強い情熱を持った人に共鳴する人は、自らの私財をなげうってまで協力することが知られています。火のような強い個性を持ち、自らを表現するものにはそれ相応の共鳴者が出現するのは必然です。
・どうして上向きに燃えるのか?
火のような強い個性を持った人間が上昇志向を持つのがそれほど不思議なことでしょうか。
・その火に触れるとどうしてほかのものまで燃えてしまうのか。
その情熱が強ければ強いほど、他人も巻き込んでしまうのは必然ではないでしょうか。それが、人というものではないでしょうか。
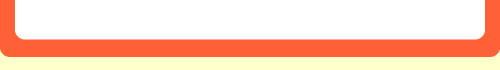
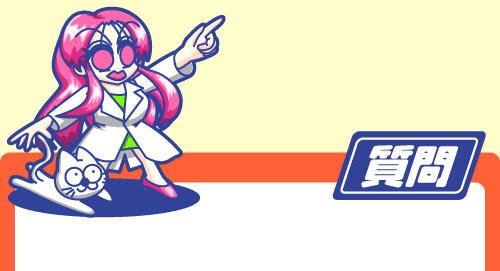
熱い缶ジュースを振ると、さらに熱く感じるのはなぜですか?
イリスさんのご質問

昔から寒い日に大人は言いました。
「そうやって縮こまってるから寒いねん。体動かしたらあったまるで。」
と。
つまり缶ジュースも動けばあたたまりますし、高石太も床の上をすべって動けばあたたまります。
島田珠代も石田靖を使えばあたたまりますし、島木譲二も缶や灰皿やきゅーきゅーきゅーべえを使えばあたたまります。
つまり動いたからあたたまったのだということです。